“眠り”の基本と快眠Q&A

ジャンセン(JANTZEN)の理念や考えに基づき、そこから派生したライフスタイルにまつわる“ヒト・モノ・コト”にフォーカスする連載企画「JANTZEN COLUMN」。今回は、私たちに欠かせない “睡眠” をテーマに、睡眠コンサルタントの友野なおさんに心地よい眠りにまつわるお話を伺いました。
季節の変わり目の寒暖差や年末に向けて忙しなくなる日々は、知らず知らずのうちに疲れがたまりがち。そんなとき、眠る前のちょっとした工夫や心がけが、翌朝の目覚めや日中の調子を大きく変えてくれることがあります。
記事末では、手軽に取り入れられる快眠のヒントをQ&A形式でご紹介。睡眠への心掛けや眠る前のひと工夫で、あなたの眠りのひと時がより心地よく、充実したものとなるかもしれません。

とものなお●睡眠コンサルタント。株式会社SEA Trinity代表。睡眠改善を専門領域とし、大学院で「睡眠×ライフスタイル」を研究。企業やアスリートへのコンサルティングなど、産業心理カウンセラーとしても活躍。著書に『ぐっすり眠れる睡眠セラピー』ほか、睡眠の知識を生活に落とし込むアプローチに定評がある。日々の習慣から“質のよい眠り”を整えることを提唱し、多忙な現代人の睡眠課題に寄り添う。
Instagram:@tomono_nao

理想的な眠りを考える上で、私たちがしばしば見聞きする“快眠”や“理想的な眠り”といった言葉。そもそも、良い睡眠ってどんなことなのだろう?
「シンプルなことですが、前提として、“よく眠れると調子がいい、逆に眠れないと体も心も疲れが残る”のです。睡眠の質と量は、毎日の心身のコンディションを大きく左右します。もちろん個人差はありますが、国立睡眠財団によると、成人の理想の睡眠時間は 7〜9時間。まずは 7時間を目安に睡眠時間を確保することが、健やかな心身のための基本です」(睡眠コンサルタント・友野なおさん、以下同)
しかし、睡眠の量(睡眠時間)を確保するだけでなく、睡眠の質を考えることも大切なのだそう。
「睡眠の“量”も重要ですが、研究では“質”を重視したほうが日中の体調や健康感により良い影響を与えることがわかっています。ただ長く寝ればいいというわけではなく、眠っている間に心と体がきちんと休まるかどうか―― これが、日中のパフォーマンスや気分、体調を左右するポイントになってきます」

世界の人々と比べても、睡眠時間が短いと言われる日本人。なぜ、日本人は眠る時間が少ないのでしょうか?
「一因として、幼少期や学生時代から睡眠の重要性、眠りについてきちんと学ぶ機会が少ないことが挙げられるように思います。昨今、人々の健康意識の高まりや働き方改革など、時代とともに価値観も変化しつつありますが、それでも睡眠を疎かにしがちな人が多いのは、今もまだ、どこかで“寝るのは怠け、寝ずに頑張るほうが美徳”といった精神が無意識に残っているからなのかもしれません」
睡眠時間が少なくなりがちな背景には、“寝ていない自慢”や“働きすぎ”といった日本の文化的・社会的要因も関係していると思われており、「徹夜もしくは、それに準ずるようなごく短時間の睡眠を誇るような風潮や、昼寝をネガティブに捉える文化がありますよね。こうしたイメージが、全体的に睡眠時間を減らす要因になっていると考えられます」と友野さん。
特に女性は、男性に比べてより睡眠時間が少ない人が多い結果も見受けられるそう。男女平等の時代になったとはいえ、外での仕事に加えて、家事や子育てなど、まだまだ女性がそれらの大部分を担っていることが多く、睡眠時間が削られやすい傾向があると考えられているようです。
睡眠は大事、ということは前提として、私たちが“眠ること”によって得られるメリットはどんなことなのだろう?
「適度な量と質を両立させた“良い眠り”がもたらす効果は、大きく“体・心・パフォーマンス”の3つに分類できます。まず、体の健康。十分な睡眠は免疫機能をサポートし、さまざまな病気にかかるリスクを下げます。体の修復力も高まるため、美容面でもプラスに働くでしょう」
友野さん自身も、“よく眠れたときは肌の免疫力が高まっているように感じる”と言います。さらに、研究では、よく眠る人は体重が増えにくいことも示されているようです。
「次に、心。よく眠れると、気分が安定しやすくなり、ストレスにも振り回されにくくなるため、なんとなく心がしんどい…というような、メンタル面の不調の改善も期待できるはず。3つ目は、パフォーマンスの向上です。集中力や判断力が高まり、仕事や学習効率がアップ。心身の健康への作用だけでなく、行動の質が変わることも大きなメリット」
良い睡眠は、ウェルビーイングを叶える上で欠かせない要素です。不安や悩みがあるときにも、睡眠を整えることは、健やかさを取り戻すための一歩に。
私たちにとって利点が多い睡眠ですが、注意点もあるようで。
「眠ることは良いことなのですが、ダラダラと寝過ぎるようなことが続いて、生活リズムが崩れると、むしろ眠りの質が下がってしまうことも。生活スタイルにもよりますが、基本的には、太陽の光をしっかり浴びて日中に活動すること、そして夜は刺激を減らして静かに過ごすことが、良い睡眠につながります」
より良い睡眠へと導く、アイテムと習慣

心地よい眠りにつくためには、“体を休息モードへ導く準備”をしてあげることが大切なのだそう。
「私たちの身体は、深部体温(内臓の温度)が下がると、自然と眠りに入りやすくなりますよ。例えば、足首まわりを温めることもグッド。足元の血行が良くなると体の中心部の温度が下がりやすく、入眠のサポートに。ただし、寝るときに靴下で足を覆いすぎると放熱を妨げてしまうので、つま先や踵が空いている睡眠用のソックスかレッグウォーマーがおすすめ。ドライヤーの温風を足首に1分ほど当ててあたためるのも◎」
さらに、香りを取り入れることも有効。アロマティックな入浴剤でリラックスしたり、寝る前にピローミストやロールオンタイプのフレグランスを使ったりするのもより良い睡眠へと導く一手間に。
「リラックスやナイトタイムのフレグランスといえば、ハーバルなラベンダーの香りが良く知られていると思います。実際に、ラベンダーの香りを15日間嗅ぎ続けたら不安感が軽減された、という研究結果もあります。ただし、眠りに適した香りに限らず、自分が“心地よい”と思える香りで構いません。とはいえ、手始めにどれを選ぶべきか迷ったら、ラベンダーがブレンドされているフレグランスや、心地よい睡眠へと導いてくれるグッドナイト系の香りを選んでみると良いでしょう」
そして、友野さんが強調していたのが、パジャマを着ること。
「気づけばスウェットやTシャツで寝てしまう人も多いですが、パジャマは“寝返りのしやすさ”や“体温調整”を考えて作られた睡眠のための衣服。毎晩必ずパジャマに着替えることで、心身が“着替え=眠るモードに入る儀式”として条件反射するように。環境が変わると寝付けなくなりがちな人も、愛用のマイパジャマがあると旅先や出張先でも眠りやすくなるはず」
加えて、“最近いいマットレスや自分に合った枕を意識して選ぶ人は増えていますが、パジャマにこだわる人はまだ少ない印象”と友野さん。
睡眠の質を高めるために、まずは眠るための環境を整えることから始めてみませんか?
【6つのグッドスリープQ&A】
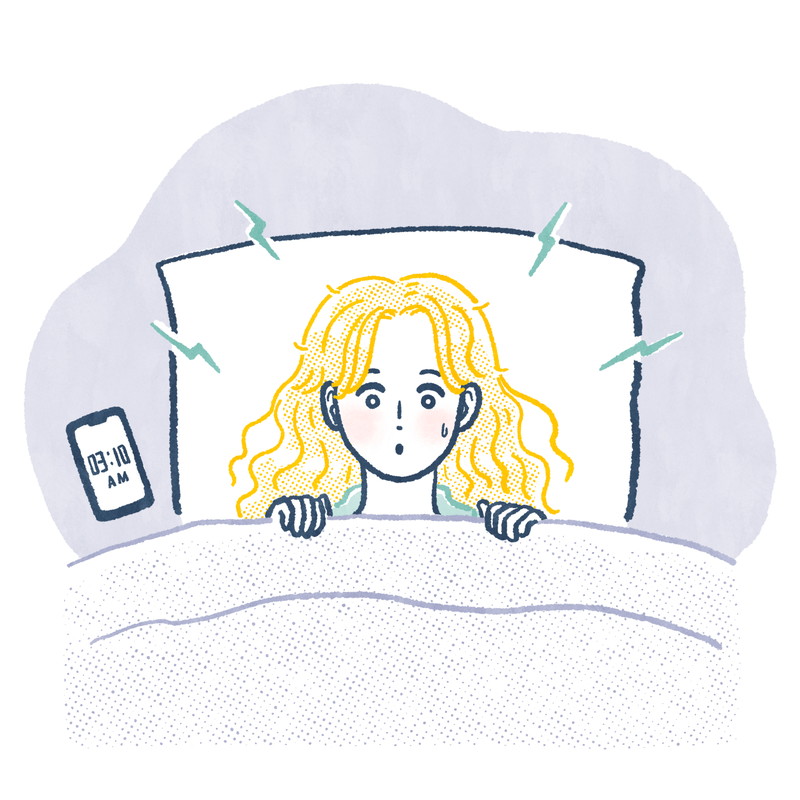
最後に、JANTZENスタッフから届いた“睡眠にまつわるお悩み”にも答えていただきました。本日から生かしたい、そして心に留めておきたい、6つのグッドスリープQ&Aです。
Q1. 疲れすぎて、何もする気がおきません…どうしたらいいですか?
A.「無理に何かをしようとせず、まずは“休む”ことを優先しましょう。お風呂に入って体を温める、あるいは思い切ってそのままベッドに入ってしまう――どちらでも構いません。“今はもう寝てもいい”と自分に許可を出すことが、結果的に質のいい睡眠につながります。疲れているときは、一旦リセット。眠ることで、心身が回復して活力も湧いてくるはず」(睡眠コンサルタント・友野なおさん、以下同)
Q2. 早朝の仕事やゴルフなど、大事な予定の前夜ほど眠れなくなります。どうすればいいですか?
A.「前日に“絶対に眠らなきゃ”と思うほど、不安で交感神経が高まり、さらに眠れなくなってしまいます。
毎日早起きする必要がないなら、無理に生活リズムを“その日だけ朝型”に合わせようとしなくてもいいんです。前日は“眠れなくても大丈夫。たった1日眠れないくらいでは、体は壊れないわ”と肩の力を抜いてみて。
仮に眠れなかったとしても、横になって目を閉じているだけで、体はきちんと休息しています。“眠らなければ”ではなく、“休めばいい”くらいの気持ちで、心を軽くしてみましょう」
Q3. 枕の高さは、どのくらいが理想ですか?
A.「理想の枕の高さは、性別や体格によっても異なります。目安として、女性はやや低め、男性はやや高めが合いやすいとされています。ポイントは、後頭部と首のすき間をしっかり埋められるかどうか。
可能であれば、店頭で実際に試しながら選ぶのがベストです。
“ピローフィッター(枕の専門スタッフ)”がいるお店なら、自分に合う高さをアドバイスしてくれます。
私的、最近一押しの枕は『ロフテー ナインセルピロー』。
セミオーダーで高さの微調整ができるため、体のコンディションや姿勢の変化に合わせてカスタマイズできるところが魅力です。ギフトとしても喜ばれそう」
Q4. ベッドに入っても全然寝つけないときがあります…
A.「Q2の回答と重なりますが、特に理由がなかったとしても眠れないときは“寝ようとしない”ことが大切です。
ベッドに入って30分ほど経っても眠りにつけないときは、いったん寝室を出ましょう。眠れないままベッドに留まると、“ここは眠れない場所”という記憶が潜在的に残ってしまうからです。
そのうえで、次の 3つのルールを試してみてください。
① 光の刺激を浴びない
スマホやPCの画面はNG。
読書や編み物、塗り絵、洗濯など単調で頭を使わない作業がおすすめ。
② 時計を見ない
“もう3時間も眠れていない…”と焦りが生まれると、さらに眠れなくなります。
③ 少しでも眠気を感じたらベッドへ戻る
“眠くなったら寝る”。感覚に従うこと。
眠ろうと頑張らないことが、心と体の緊張を解き、自然な眠りへと導いてくれるはず」
Q5. 長時間の移動やフライト中に眠るとき、用意しておくといいものは?
A.「次のようなアイテムを活用するのもおすすめです。
蒸気で目元を温めるアイマスク、耳元を温めるグッズ、レッグウォーマー、ネックピロー、マイスリッパ(移動時に履いていたシューズから履き替える)、ロールオンフレグランス等のリラックスできる香りのアイテム
小さな工夫で、飛行中でも心地よく体を休めやすくなります」
Q6. 時々、13~17時間も起きられないことがあります…
A.「まず考えられるのは、普段の睡眠が足りていない場合や、もともとロングスリーパーの可能性です。長時間眠ってしまうのは、普段の睡眠不足がまとめて出ているだけかもしれません。
改善のために、まずは次のポイントを意識してみましょう。
① NOT TO DO LISTを作る
やらないことを決め、睡眠時間を少しずつ増やす。5分ずつでもOKです。日々の小さなベビーステップで、無理なく睡眠習慣を整えます。
② パジャマを整える
睡眠の質は、パジャマや寝る前の準備で大きく変わります。
コットンのパジャマを着る、寝る1時間前にお風呂に入る、枕を整えるといった基本を意識するだけでも、眠りの濃度や質を高めることができると思います」
日々の心掛けで、“より良い睡眠”を叶える。
「私は、睡眠によって人生が変わり、それをきっかけに今の活動に至りました。睡眠の質は、心と体の健康の土台です。毎日のウェルネスの基礎として、ぜひ本コラムでご紹介した内容を取り入れてみてください」(友野なおさん)
何気ない毎日の中で、なかなかきちんと向き合えないけれど、私たちが健康的に生きる上で大切な睡眠のこと。
お悩みがある人はもちろん、特に意識してこなかった人も、枕の高さを見直したり、パジャマを整えたり、寝る前に光や時計の刺激を避けたり――。今日からできることを1つずつ試して、心地よい眠りを手に入れてみましょう。
illustration_Yuki Tomomatsu / edit & text_Ryoko Suzuki


